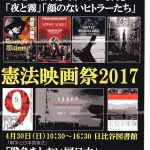(弁護士 後藤富士子)
1 朴正煕大統領の長期独裁体制 ――「維新憲法」
1969年、朴正煕大統領は、三選改憲で政権を長期化したが、さらに永久政権を企て、72年10月17日、既存のすべての民主主義制度を停止して超法規的非常措置「維新」を宣布した。各大学の構内に戦車が進駐し、維新の宣布と同時に無期限休校命令が出された。そして、同年12月、憲法上の国民の自由と権利を暫定的に停止させることができる大統領の「緊急措置」を定めた維新憲法が公布された。
文在寅は、大学法学部1年生であった。既存の法典や法学書はゴミ同然になってしまったのだから、「これでも法学が学問だと言えるのか」「そもそも法学に学ぶ価値があったのだろうか」という疑問が法学部生たちを押し潰した。翌年春に授業が再開されたが、憲法の教授は、休校中に新たに維新憲法の本を書いて講義に使った。
73年後半から、全国で維新反対闘争が起きた。改憲請願100万人署名、緊急措置1号、4号の発令、74年の全国民主青年学生総連盟事件(政府転覆を企てたとしてメンバー等180人がKCIAに逮捕され非常軍法会議にかけられた)、75年の人民革命党再建委員会事件(党を再建し、民青学連の国家転覆活動を指揮したとして23人が国家保安法違反で逮捕され、8人が死刑となった)などが立て続けに起こった。文が大学で維新反対デモの首謀者の1人として逮捕され、大学を除籍されたのも75年4月のことである。
79年10月26日、朴正煕大統領が暗殺された。全斗煥や盧泰愚などが中心になって軍事クーデターを起こし、崔圭夏大統領を引きずりおろして間接選挙で全斗煥を大統領とする「第五共和国」政権を樹立した。80年になると、大学を拠点にして全国的に反独裁・民主化闘争が澎湃として巻き起こり、復学した文も熱心に活動した。5月17日に除外されていた済州道にまで非常戒厳令が拡大されると、文は、戒厳布告令違反で再び拘束された。留置所で司法試験合格を知らされ、同年8月に大学を卒業し、司法研修院を経て、82年8月、盧武鉉と合同法律事務所を構えた。
2 全斗煥大統領の「護憲措置」
87年1月、釜山出身のソウル大学生朴鐘哲が取調中の拷問で死亡した事件が発生し、2月7日、全国各地で一斉に国民追悼集会が開催された。釜山の怒りは沸騰し、警察が会場を完全封鎖する中、急遽、別の場所(路上)で追悼集会を行ったが、警察が白骨団(私服警察官で構成された鎮圧部隊のあだ名。一般警官と区別するために白ヘルメットを着用)とともに押し寄せてきた。恐れ動揺する市民や学生を守るために、釜山民主市民協議会の役員らは市民・学生と警察の間に割って入り、道路に腰を落として座り込みを始めた。盧武鉉と文在寅も座り込み、警察の催涙弾を浴びながら、ごぼう抜きにされて鶏舎車(護送車)に放り込まれ、釜山市警の対共分室(スパイ事件の捜査を担当する部署がある別棟)へ連行された。盧武鉉に逮捕状が請求されたが却下されると、検察は何度も非公式に令状請求するなど、韓国の法治主義の現在地を露呈した。
4月13日、全斗煥大統領は、国民の民主化要求を拒否して一切の改憲論議を停止させる「護憲措置」を発令したが、国民の民主化の熱気に油を注ぐ結果になった。民主化を求める時局宣言(政府が民意に背を向けたり、社会的混乱が起きたときなどに、知識人など社会的影響力のある人々が憂慮を伝えて解決を促すために発表する宣言文)が洪水のように発表された。5月には、全国のすべての民主化運動団体に野党が加わって「民主憲法争取国民運動本部」(略称「国本」)が結成され、盧武鉉弁護士は「釜山国本」の常任執行委員長になった。6月、全国で連日デモが展開され、ついに同月29日、全斗煥政権は、①大統領の直接選挙への改憲、②軍事独裁の平和的政権移譲、③金大中赦免復権と時局事犯の釈放などを骨子とする特別宣言を与党盧泰愚代表に発表させた。
こうして韓国の市民社会は、「6月抗争」により軍事独裁政権を倒したのである。
3 盧武鉉大統領を弾劾から救った「民意」
2002年、盧武鉉は大統領選を制し、翌年1月、文在寅は、「権威主義の打破」を掲げる参与政府(盧武鉉政権)の民情首席秘書官就任に応じた。権威主義の体制が打破されて政治的・市民的民主主義が完成するには、大統領が「憲法や法律にない、超越した権力」を放棄することだと意識された。具体的には、政権の目的のために権力機関を利用しないところから始めなければならなかった。この盧武鉉政権が目指したものこそ、権力分立を中核とする立憲主義であろう。
ちなみに、今年10月から徴用工をめぐる韓国大法院判決が相次いだが、むしろ、朴槿恵前政権の意向をくんで判決を遅らせたとして、職権乱用などの容疑で前大法院判事2名について、逮捕状が請求されたと報じられている。2017年の「就任の辞」で「国を国らしくつくる大統領になる」と約束した文在寅大統領が、盧武鉉政権のやり残した宿題に取り組んだ成果が表れているように思われる。
ところで、2004年3月、盧大統領の弾劾訴追案が国会で可決された。弾劾は、大統領、国務総理、法官(裁判官)など身分保障を受けている公務員の非行について、国会在職議員の過半数の発議で訴追され、3分の2以上の賛成で可決されると、憲法裁判所で審理され、裁判官9名のうち6名以上の賛成によって弾劾が決定される。
大統領の委任を受け、文は、代理人団を立ち上げ、本格的な活動が始まった。法律的に緻密な弁論をすれば絶対に勝てると確信した。弾劾は多数党の数による横暴というほかなく、法的根拠がないことは明らかで、民意に逆らった多数党のクーデターとして、民主憲政の危機が認識された。法廷の弁護活動だけでなく、憲法学者をはじめとする法律の専門家に働きかけて弾劾反対意見を表明してもらうことができた。
弾劾に反対する市民たちのろうそく集会も開かれた。弾劾裁判の政治的性格や憲法裁判所裁判官たちの保守的な傾向を考えると、世論で圧倒する必要があった。文は、インタビューに応えて、「憲法とは何なのか。はるか遠くの高みにあるものではないはずだ。国民がもつ、民主主義に対する最も普遍的で素朴な思い、それを象徴的に表したものが憲法だ。つまり憲法の解釈も、一般国民の民主主義や法に対する意識から出発しなければならない。それが憲法に反映されなければならない。そうであるなら、街頭に出たこの大勢の市民たちによる弾劾反対のろうそく集会が、すでに弾劾裁判の進むべき方向を示しているのではないだろうか」と述べている。
弾劾裁判の途中の4月15日、第17代総選挙があり、政権与党「開かれたウリ党」が単独過半数(299議席中152議席)を得て第一党となった。これは、弾劾に対する、恐ろしいほどの民意の審判であり、弾劾裁判の判決への決定打と思われた。そして、5月14日、憲法裁判所は、弾劾棄却の判決を言い渡した。
4 与えられた日本国憲法
戦前の日本において治安維持法が弾圧したものは、「反戦」と「主権在民」である。共産党は「戦争反対」と「主権在民」を主張して、絶対的天皇制権力により殺人的・壊滅的な弾圧をうけた。だが、これらの暴虐の根拠は、日本国憲法で除去された。すなわち、日本国憲法により「国民主権」と「絶対的平和主義」が実現したのである。
しかし、問題は、韓国に比べればわかるように、国民が民意により勝ち取ったものではないことにある。共産党の野坂参三がGHQを「解放軍」と規定したというのも興味深い。また、9条については、GHQによる「刀狩り」にすぎず、それゆえにアメリカの安保政策に組み込まれて換骨奪胎の体を露呈している。さらに、4月28日は、本土では「主権回復の日」とされる一方、沖縄では「屈辱の日」とされ、日本国憲法は適用されなかったのである。
ところで、今日「慰安婦」「徴用工」などの歴史問題が噴出している。それは、日本が過去の歴史問題と真摯に向き合ってこなかったことのツケであり、その問題の現れ方も、解決方策についても、韓国と日本の差は大きい。ちなみに、文大統領は「韓日関係には過去の歴史問題がある。いつでも火がつくし、完全に解決したとみることはできない。歴史問題のために、韓日を未来志向的に発展させる様々な協力関係に問題が起きてはいけない」と述べている。この現実政治の落差は、憲法を自ら闘い取った国民と、与えられた憲法に寄りかかって安穏と過ごしてきた国民の差ではないかと思われる。
※本文で韓国に関する記述は『運命 文在寅自伝』によっており、誤解があるかもしれません。
〔2018・12・5〕